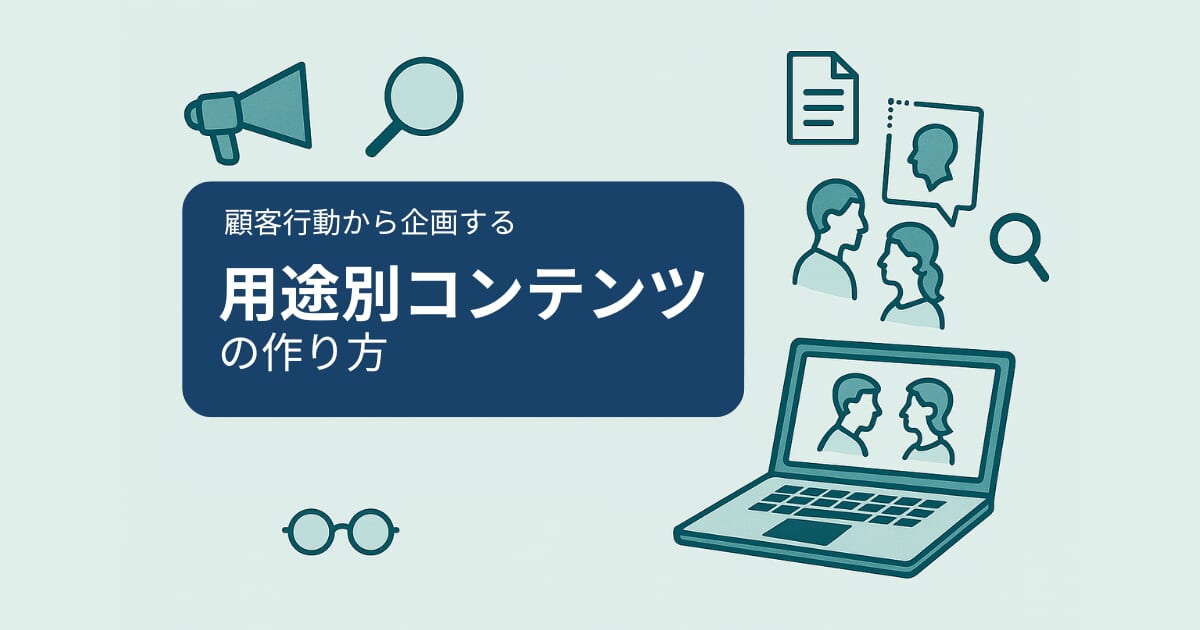サイトエンジンはコンテンツマーケティングの支援を数多く手がけてきましたが、その経験の一環として、自社で運営するSaaS「ラクテス」でもコンテンツマーケティングに取り組んでいます。
ラクテスはお客様が独自の筆記試験を簡単に作ることができるというSaaSです。類似サービスがほとんどない領域のため、製品カテゴリ自体が認知されておらず、明確な検索ニーズが少なく把握しにくい状況でした。そこで手探りの状態から始めたのが、用途・利用シーンを丁寧に示すストック型コンテンツを増やす方法です。
この記事では、私自身が自社SaaSで試行錯誤したなかで得た知見をもとに、用途別コンテンツの作り方や注意点をまとめています。運営されているサイトや業界の状況に合わせてご活用ください。
用途をコンテンツ化するとはどういう意味か
「用途別コンテンツ」は、一般で使われていない言葉です。(ほかにもすでに使ってらっしゃる方がいるかもしれませんが確認していません)どのようなものかというと、製品やサービスが実際にどのようなシーンで役立つのか、具体的な利用例を分かりやすくまとめたページを作成することを指します。たとえば「○○という職種の採用試験でオンラインツールを活用する方法」「△△業界のコンプライアンス教育にテストサービスを導入するには」のように、「誰が」「何に困っていて」「このサービスがそれをどう解決するのか」を1つの用途として切り出し、それを1ページとして独立させていくイメージです。
用途別コンテンツが通常のノウハウ記事と異なるポイント
購入に近い悩みを抱えている“自分ごと化”しやすい人を集客できる
ノウハウや業界トレンドをまとめた記事は情報収集している見込み客を広く集客できる点で有益です。一方で、用途別コンテンツはより具体的な悩みについて細分化して書くので「自分の業界や自社の状況に合いそうだ」と思ってもらえる人を集められるという特長があります。
ニーズが顕在化していない状態の人にアピールできる
既存の製品カテゴリが認知されていない場合や、そもそも検索キーワードが確立していないようなケースでは、直接“このシーンで役立ちます”と打ち出したページのほうが潜在的な顧客に響きやすいことがあります。
たとえば、「採用時の人材に見極めに課題がある」と思っていた企業が、偶然「採用ミスマッチを減らすためのオンラインテスト活用」という用途別コンテンツを見つけて「こんなソリューションがあったのか!」と興味を持つようなイメージです。そもそも「オンラインテスト」という選択肢が頭に浮かんでいない場合でも、「採用ミスマッチを減らす方法を探していたらヒットした」という流れでページにたどり着き、サービス導入のきっかけにつながることがあります。
フロー型ではなくストック型の性質を持つ
時事ネタやノウハウ情報よりもニーズの規模が小さい一方で、時間が経過しても安定して集客し続けることができます。用途別コンテンツは長期的に“悩みがある人”を呼び込み続けるストック型コンテンツとして機能します。
用途を軸にしたコンテンツが重要だと感じた理由
ラクテスは類似製品が少なく、一般的なノウハウ記事やまとめ記事で情報に興味を持ってくれたとしても、サービスの導入検討につながりにくいと感じました。製品カテゴリ自体が知られていないため、ノウハウなどを読んだあとにサービス案内をしても、悩みとサービスを関連付けしにくいという問題がありました。
そこで、ノウハウというよりかはどちらかというと課題自体にフォーカスした利用シーンを含むストック型のコンテンツを増やすことで、「このケースなら自社の問題を解決できるかもしれない」とピンときてもらう仕掛けが重要だと考えました。漠然と情報収集している段階のユーザーが、たまたま“自分の悩みに直結するシーン”を見つけ、「こういうやり方があるんだ」と気付く機会を提供できれば、結果的に問い合わせや導入検討へ進む可能性が高まります。
用途を発見するサイクル
初期段階:顧客がいないときの仮説づくり
まだ実際のユーザー事例がほとんどない段階では、自社サービスの機能や強みを一覧化し、「こんな場面や課題で役立つかもしれない」という想定シチュエーションをリストアップしました。たとえば、オンラインでテストを実施できるサービスであれば「採用試験」「社員研修後のテスト」「昇進昇格試験」「資格試験」のように、それぞれの用途を解説するページを用意するイメージです。
成功事例がないからといって情報を載せないのではなく、「こういうメリットを得られる可能性が高い」といった形で仮説を提示し、読者に「自分の課題に近そうだ」と感じてもらえるようにすることが大切だと考えて、想定される使い方を書いていきました。
なお、どれくらいのニーズがあるか、ニーズの量はあまり気にしておらず、「日本全体で考えたら年間で何人かはこの悩みを持つのではないか?」くらいのイメージでつくっています。
顧客が出てきたら“使い方”を徹底観察
最初の導入事例が生まれたら、私は積極的に担当者や実際に使っている現場の方に話を伺いました。導入の背景、課題、どのように運用しているのかなどをできるだけ具体的に教えていただきます。「こんな使い方があるんだ」と驚くようなことも珍しくありません。
こうして得られた生の声は、新たな用途を発見する最大のヒントになります。顧客視点でどういった使い方がありえるかを考えられるようにするには、とにかく顧客との接点を増やすことが重要です。インタビューさせてもらうことが難しい場合には、サービス利用方法を行動履歴のデータから確認する方法もあります。
発見した用途をページ化
私たちが想定していなかった使われ方を知るたびに、「そのニーズは他社にも共通しているかもしれない」と考え、すぐに内容を抽象化してページを作っていきました。結果として少しずつお問い合わせいただける量が増えていきました。私たちが想定していなかった使われ方を知るたびに、「そのニーズは他社にも共通しているかもしれない」と考え、すぐに内容を抽象化してページを作っていきました。結果として少しずつお問い合わせいただける量が増えていきました。
大切なのは、単に「こういう機能をこう使いました」だけではなく、「もともとどんな課題があって、それがどう解決されたのか」をストーリーとして紹介することです。
課題→導入→効果の流れがはっきりしていると、同じような悩みを抱えている読者が「これなら自分のところにも導入できそうだ」と思い描きやすくなり、そのまま問い合わせや利用登録につながるケースが増えました。
似た用途へ横展開する
ある用途が当たれば、その事例を基点に別の業界・職種へ応用できないかを検討していきます。加えて、アクセス解析で「どの用途のページが実際に顧客獲得につながったか」を確認し、成果を出しているテーマを横展開することも大切だと考えています。
弊社サービス「ラクテス」での用途別コンテンツ事例
サイトエンジンが運営しているオンラインテスト作成・運用のSaaS「ラクテス」では、初期の段階から「採用や研修で使えそう」「社内資格試験にも応用できるかも」といった用途をリストアップし、それぞれに合わせたページを整備することに注力しました。こうしたページをまとめていくうちに、「自分の業界や職種でもこう使えるのではないか」と興味を持つ人が増え、思わぬ形で新たな課題が解決できる事例が次々と生まれるようになっています。
サンプルテストの公開
まず取り組んだのは、具体的なサンプルテストを複数用意して、実際にテスト問題の一部を公開することでした。たとえば、中途採用向けに職種ごとの基礎知識を測定するテストや、新入社員研修のあとに使えるテスト、情報セキュリティやコンプライアンス研修の定着度をチェックするテストなど、すぐに導入イメージが湧くようなテーマをピックアップしています。それぞれのサンプルテストが様々な用途を対象にしたページとなります。
以下はテスト一覧の画面です。能力・スキルや業界・業種などからテストの絞り込みができるようになっており、クリックするとテストごとのページに遷移する仕組みにしています。

ユーザーが自社の状況に近いものを簡単に見つけられるようにしています。
アクセス解析のデータを見ながら、どのサンプルテストのページが顧客獲得に結びついているかを分析しています。ラクテスの場合は、プログラミング言語別のサンプルテストをいくつか用意してみたところ、ある言語に対して顕著に高い登録率や課金率が確認できました。そこで「他の言語でも同じようなニーズがあるかもしれない」と考え、さまざまなプログラミング言語用のテストを増やしていった結果、全体の顧客獲得数が伸びたという実例があります。
こうした横展開の取り組みを続けることで、サンプルテストの活用はさらに広がり、サイト全体の成果にも大きく貢献するようになりました。
利用シチュエーション・課題別ページの作成
次に力を入れたのは、採用担当者のこの課題向け、研修担当者向けなど、実際の業務シーンを想定したページを作ることでした。たとえば採用担当者向けページでは、大量応募がある場合でもオンラインテストを使えばスクリーニングを効率化できる流れを具体的に説明しています。
以下は実際に制作したページの例です。(該当ページ:ラクテスの活用例)

同様に研修担当者向けのページでは、新人研修や中途社員向け教育でオンラインテストを組み合わせることで、理解度を可視化しやすくなったり、学習意欲を高めやすくなった事例を詳しく載せました。
こうしたシチュエーションごとの情報を細分化して提示することで、お問い合わせフォームから具体的な課題を記載したうえでご連絡いただける方が増えた印象があります。
職種・業種・業界別ページの充実
さらに、業界特有の資格や専門知識を必要とする場面に着目し、医療事務、製造業、ITエンジニアなど、それぞれに適したテスト活用法を深掘りするページを作りました。
たとえば、以下の画像のように、特定の職種に求められるスキルセットを紹介し、関連したサンプルテストを紹介するようなページをつくっています。この画像の例は「プロジェクトマネージャーを採用する」という用途のためのページです。
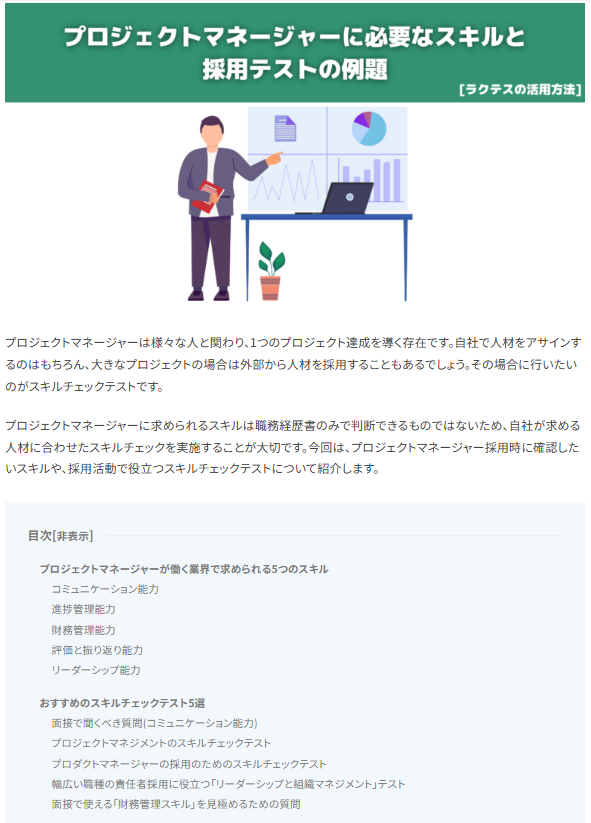
このように職種・業種ごとのページを用意すると、たとえばITエンジニア採用に力を入れたい企業が「プログラミング言語別にサンプルテストがあるなら、すぐに導入してみよう」という判断をしやすくなり、実際に登録や問い合わせへつながりやすいという手応えを得ました。ユーザーから「こういう試験を作りたい」「この業界でも同じようなニーズがある」といった声をいただくたびに、新しいページを追加してより多くの用途を取り込み、その結果としてさらに幅広い層からのアクセスが集まる好循環を生み出しています。
なぜ“現場の悩み”を最優先にするのか
コンテンツマーケティングでは、SEOでの集客数確保のためにキーワードの月間検索回数や競合調査などからキーワードを選定して記事を書いていくプロセスが採用されることがありますが、今回ご紹介した用途別コンテンツの制作例ではキーワードの検索回数はほぼ無視しています。
キーワードを意識して書いた記事でも一定の流入は見込めますが、深い課題を抱えている人は「自分と同じ境遇」「自分と同じ業界の事例」を探していて、そうした細分化されたニーズはGoogleの月間検索回数としてはすごく小さい数値になるか、回数が表示されないです。
現場で教えてもらった生の声を起点に新しい用途を発見し、サイト内で細かくページ化しておくと、深い課題を抱えている人たちに直接アプローチできます。流入数は小さいものの成約率は高いという状態を目指しています。
実際にラクテスでは、「こんなサービスを提供している会社があるとは思わなかった」と商談の際におっしゃっていただけるケースがあります。現場の声を拾う姿勢を持ち、常にページを拡充していくことが、成果につながるコンテンツマーケティングの土台になると実感しています。
用途をコンテンツ化するときの注意事項
用途別コンテンツは本当におすすめなのですが、よくコンテンツマーケティングで採用されるハウツー記事とは異なる結果になります。以下のようなポイントをあらかじめ理解しておくと導入がスムーズだと思うので共有します。
流入の母数が確保しづらい
用途別コンテンツを作る際には、キーワードの検索ボリュームは考慮しないです。たとえば「この課題はニッチだけれど、困っている人は絶対いるはず」と思えるテーマに絞り込むと、そもそもの検索数が少ないため、ページが上位表示されてもほとんどPVに繋がらない場合があるのです。
ただ私は、一年に数回でも「まさにこの課題を解決したかった」という人に見つけてもらえれば十分だと考えています。大きなPVを狙うのではなく、深い悩みを持つ人の背中を押せる“超ニッチ”なページこそ、長期的に見れば価値が高いと思っています。
資料請求や無料登録などが増えても売上につながらないことも
用途別コンテンツは、具体的な悩みを持つ読者を集めやすい反面、その先の「有料化」まで結びつかないケースもあります。ラクテスでも、無料プランの登録が大量にあるものの、有料プランへの切り替えはほぼないというページが存在しています。
悩みが具体的でもお金を払うほどの深刻さがないというユースケースもありますので、流入数やリード獲得数だけではなく、売上貢献も確認するようにします。
継続的な更新や改善が不可欠
用途別コンテンツは一度作ったら終わりではなく、時期や状況に合わせて内容をアップデートすることが欠かせません。
政治・経済など一般常識のサンプルテストをラクテス上で公開していたのですが、情報が古くなり登録率が下がってしまった経験があります。
最新のトレンドや法改正などが関連する分野では、特に情報を更新しないと「このサービスは最近の動向を反映していない」と思われかねません。せっかく訪れたユーザーに「参考にならないページだ」と判断されるのはもったいないため、最新のトレンドを積極的に取り入れて、常に情報鮮度の高い状態を維持することを心がけています。
まとめ
費用対効果や成果を出すまでのスピードを意識したとき、まず取り組むべきコンテンツマーケティング施策は「ハウツー記事を量産すること」ではないかもしれません。
ラクテスでは、「用途の発見とページ化を繰り返す」という方針を打ち出した結果、より購買意欲の高いユーザーを取り込みやすくなったと感じています。
- 初期は仮説から用途別ページをつくり、少しずつ実例として収集した用途を取り込む
- 顧客から見つかった想定外の使い方をすぐに横展開し、専用ページを追加
- アクセス解析で顧客獲得につながった用途を洗い出し、横展開して拡張する
このサイクルによって、コンテンツの幅が広がり、かつ深い悩みを持つ読者へ効率的にアプローチできるようになりました。もし「ハウツー記事をいくら書いても、なかなか成果につながらない」と感じているなら、ぜひストックとして積み上がっていく用途別コンテンツを試してみてください。